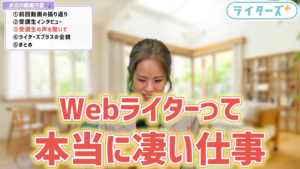こんにちは、町屋です。
育児ブログを見て頂きありがとうございます。
当記事について
- 知育玩具とは?
- 知育玩具の与え方とタイミング
- 年齢別の知育玩具について
- 知育玩具の体験談
こんな悩みを解決します。
知育玩具って0歳からでも使える?
人気の知育玩具って何?
モンテッソーリやつみきが定番かな?
 町屋
町屋知育玩具の効果とタイミング | 早期教育におすすめ?【1歳・2歳・3歳】








本当に楽しく遊べるのかな?なんてことも気になりますよね。
知育玩具の効果や、与え方、実際に知育玩具を与えた体験談をまとめました。
知育玩具のはじまりとその定義
まずは、知育玩具の基礎知識から。
知育玩具のはじまりは、ドイツの教育学者・フレーベルが1838年に考案した「恩物(Gabe)」だと言われています。
フレーベルの恩物は、子供が自分の力で自然に学べるように設計されているのが特長。
現在でも日本知育玩具協会による知育玩具の定義は、「長く遊べる良質な玩具であって、遊びを通して自然の法則を学び、生涯必要となる集中力、意欲、社会性、創造力、やり抜く力を身につける、文化的価値のある玩具」であるとされています。
知育玩具の現状
2018年の「子供へのクリスマスプレゼントについての調査」より。
「今年、末子のお子さんにどんなプレゼントをあげたいですか?」という質問に対してもっとも多かった回答は「知育玩具」でした。
2018年の玩具市場における知育玩具の伸び率は前年比約102%。
2019年は前年度より下がっているものの、プログラミング教育必須化をうけてプログラミング関連を中心に知育玩具は好調といえる結果になっています。
参照:
>>コネヒト株式会社「子供のクリスマスプレゼントの意思決定者は「ママ」が約80%。 人気のプレゼントランキング第一位は「知育玩具」【ママリ調べ】」
>>日本玩具協会「2019年度の玩具の国内市場規模は8,153億円」
知育玩具の効果
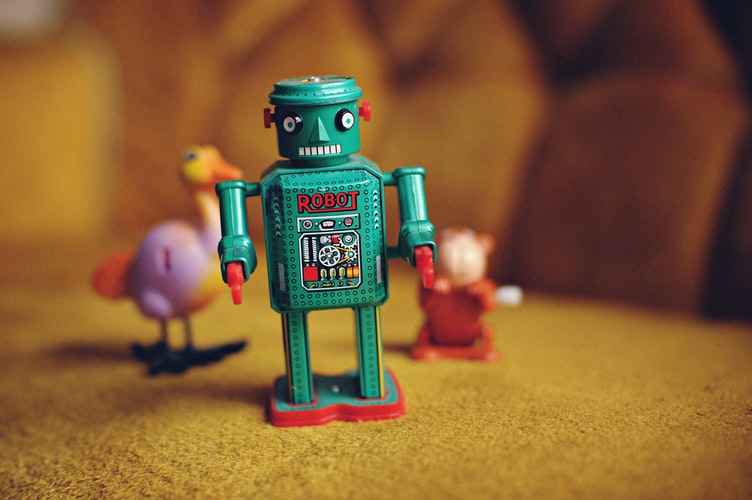
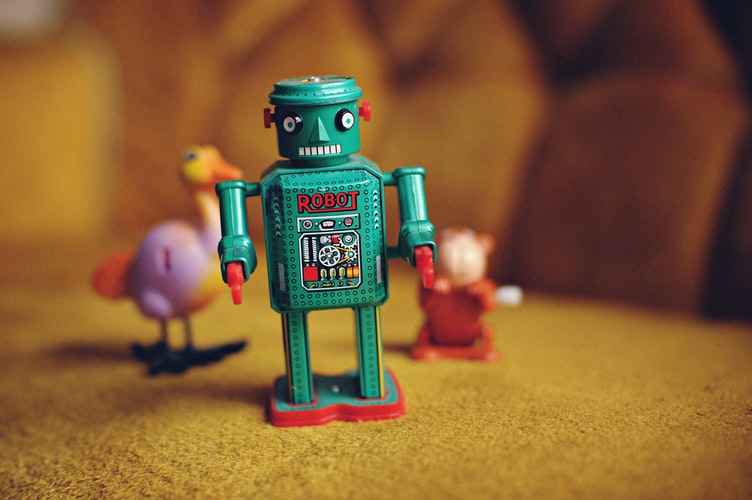



否認知能力が身につく
上記の通り、日本知育玩具協会の定義では
- 自然の法則を学び
- 集中力
- 意欲
- 社会性
- 創造力
- やり抜く力が身につく
とされています。
知育玩具の効果は、知識の習得ではなく、考える力、生きる力を身につけることにあるのです。
そういった能力は否認知能力と呼ばれています。2017年の学習指導要領改訂によりその幼児教育における重要性が改めて注目されている能力です。
参照:
>>小田急百貨店「知育玩具とは?選び方や年齢別おすすめ玩具をアドバイザーが伝授」
早期教育的な知育に効果はない



慶應義塾大学環境情報学部教授で言語心理学者の今井むつみ先生の研究。
早期教育は一時的に効果があるように見えてもそれは長期に渡るものではなく、むしろ遊ぶ時間を奪うことによる害のほうが大きい。知育玩具を与える際には、年齢に合ったものであること、楽しく遊べるものであることが大切です。
参照:
>>日経DUAL「本当に効果ある早期教育は? 子どもは遊びから学ぶ」
知育玩具の与え方・適切なタイミング








0歳~1歳
0歳~1歳は、聴覚、視覚、触覚など五感に訴えるものが良いでしょう。
そこから多くの情報を得て、発達が促され、その後の基礎を築いてくれます。
- ベビーのプレイマット
- 絵本
- 鈴の入ったぬいぐるみ
2歳~3歳
指先が器用になってくる2歳~3歳の時期は、手や指を使う知育玩具が良いでしょう。
指先を使うことで、脳への刺激にもなります。
- つみき
- ひも通し
- パズル
- ペグさし
4歳~6歳
この時期は、数、言語、ロジカルな思考に訴えるものが良いでしょう。
勝ち負けのあるものもおすすめです。
- すごろくのようなゲーム
- カルタ
参照:
>>伸芽会「幼児教育に取り入れるべき「知育」とはなにかを解説」
知育玩具の体験談・子供に選ばせてみる



好奇心が満たされる
そのお母さんは、基本的に面白いものを選ぶのではないかと思っていたと言います。
面白さの基準は「好奇心が満たされる」こと。
だからこそ、その年齢に合った段階の知育玩具を自然と選ぶのではないかということでした。
知育玩具はあきない
そして、そのように選んだ知育玩具はあきずによく遊ぶそうです。
大きくなっても思い出したように出してきて遊ぶこともあれば、他の玩具と組み合わせて新しい遊び方をすることもあったということでした。
子供にとって知育玩具は楽しいおもちゃ
優れた知育玩具であれば、子供にとっても楽しいはず。
なぜなら、子供の好奇心を刺激し、遊びが学びになるのが知育玩具だからです。
子供が興味を持たないものは、年齢や興味があっていないのかもしれません。
知育玩具の体験談・実際に活躍した知育玩具


先述のお家で実際に赤ちゃんの頃から活躍した知育玩具をいくつかピックアップしてもらいました。
オーボール
カラフルな網目状のボール型おもちゃです。
赤ちゃんのうちはつかんで振り回す、なめる、握るなどからはじまり、転がす、投げるように。
そのうち、潰した反動を楽しむ遊び方も。
「一人遊び」から、「転がして一緒に遊ぶ」に移行する様子が見られたそうです。
型はめパズル
同じ形の穴にピースを入れる箱型のパズルです。
最初の遊び方は、ピースを掴む、箱のふたの開閉など。
型はめをするようになると、入った時にピースが落ちて音が鳴るのを喜んでいたそうです。
プラステン
棒にカラフルなリングを通すおもちゃ。
サイコロやひもが付属しています。
指先の遊び、色、数の把握に。
赤ちゃんでも、つかんだり、真ん中の穴に指を入れたりして楽しんでいたそうです。
リングをおままごとのお金のかわりにしたり、ゲーム性を持たせて遊ぶなど、発展した遊び方もするようになったということでした。
まとめ



子供は遊びから学びます。
あまり知育を意識しすぎず、子供にとって楽しいものを選ぶのが一番なのかもしれませんね。
おすすめサイト:
>>ママ必見!?おもちゃのレンタル【キッズ・ラボラトリー】
![]()
![]()